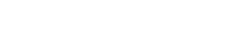5月14日6時半。横浜の晴れ渡った空に、世界のトップ・パラアスリートたちの鼓動が響いた。パラトライアスロンのスイムスタート地点に向かう、ウェットスーツ姿の鍛え抜かれた各国選手たち。その中でもひときわ背の高いブライアン・ノルベルグ(アメリカ)は、緊張した表情ながらも、体の動きはむしろ軽やかだ。
「僕のレースでは、常に最後に勝機がある」これまで多くの世界のパラトライアスロン大会を戦い、この9月、リオパラリンピック(ブラジル)への出場に手をかけるノルベルグの強みは、最終種目のランだ。
ノルベルグは脳性まひにより右手と右足に運動障害をもつ。パラトライアスロンは、障害の程度によって選手が5クラス(PT)に分かれるが、ノルベルグは立位で最も重度とされるPT2の選手である。
レースは6時55分に第1ウェーブからスタート。スイム(750メートル)→バイク(20キロメートル)→ラン(5キロメートル)の順でフィニッシュを目指し、クラスごとに速さを競い合う。スイムスタートは、特別に設置された桟橋にスタート台が設けられ、パラ選手は水に入ってスタートする。スイムコースは海上のため応援の声が届かないが、会場全体が耳を傾け、号砲を待つ。
スイム〜バイク間、バイク〜ラン間にある「トランジション」も、いかに迅速に効率よく次の種目に移るかがタイムに大きく影響する、緊張の一瞬である。
声援を贈るには、バイク、ランの競技中がチャンスだ。沿道からバイクやランで力強く走り去る選手の背中に応援の声をかけると、まるで声を乗せて走ってくれているような気持になる。
フィニッシュしたノルベルグ選手は、激しいレースの疲れを見せない満足した笑顔で語ってくれた。
ーーフィニッシュおめでとうございます。レースを振り返っていかがでしたか?
「今年のレースの中でも今日が一番楽しかった!前の大会から4分も縮めることができた。昨年の横浜と違って天気も良くて(苦笑)。今大会は同じクラスの出場者が皆強豪ばかりだと分かっていた。でも僕はいつも通り、最後のランで勝負をかけるつもりだったよ」
ーーランとトランジションが強みですよね。今日は戦略通りに進みましたか?
「そうだね。ほとんど予想通りに進んだと思う。でも、やはり他の選手が凄く早かったので、バイクを終えてトランジションに入るときに、既に何人かがランコースに走って行くのが見えた。だから、何としてでも差を縮めるために、ランは最初からフルスピードで行かなきゃいけない心づもりができた。結果的に自身のタイムを縮めることになったので、そういう意味ではラッキーだった」
ーーノルベルグ選手にとって、今回のレースの難所はどこでしたか?
「スイムは常に自分の課題なんだ。僕はスロー・スイマーだから。特に今日のコースは水がしょっぱく感じた(笑)。まあそれはいいけれど。僕の現在住んでいるアイオワ州は、近くに海がないので練習の機会が限られているのが悩み」
ーー水がしょっぱかったと(笑)。横浜のコースは、他の会場と比べてどう感じましたか?
「横浜のコースは素晴らしいよ。ここほど、僕たちパラトライアスリートも「プロ」と見なして扱ってくれる会場はあまりない。健常者のトライアスロンと同じコースで競技できるのも良い点だし、トランジションエリアの整備なんかは本当にしっかりしていてありがたいよ。バイクのコースも非常に走りやすかった」
ーー次の目標はどうお考えですか。またそれに向けてのトレーニングは?
「実際まだわからないんだ。この大会前の大会で、リオの出場水準には達していて(注:ノルベルグ選手は16年3月のサラソタ大会で、既に米代表水準である「Confirmed」の資格を獲得済)、ただそれで自動的に代表になれる訳ではなく、6月30日の代表選考期間終了を待って、正式に委員会で代表が決まるから」
ーーなるほど。でも、狙いはリオでしょうか?
「まあもちろん(笑)。課題はスイムの強化だ。今は良いコーチがついているので、集中してトレーニングしたい」
ーー米国で障害をもつ子どものスポーツ支援をされていますよね。障がいの有無かかわらず、若いスポーツ世代へのメッセージはありますか?
「そうだね。アメリカのDare2Tryという障害者スポーツ支援団体の活動で、数人の子ども達の指導にもやりがいを感じてる。でも僕が言えることといえば、とにかくできることをやる。トレーニングを重ねる。それだけ。とても良い大会なので、来年の横浜のトライアスロン・パラトライアスロンに出るつもりで必死にトレーニングすることだね。
ーーありがとうございます。
今回の競技では強豪の中で5位という結果だが、ノルベルグ選手のコメントは自身の達成感と周囲への感謝の言葉で埋め尽くされていた。
取材のお礼を伝えると、左手で競技バイクを引いたまま、握手のために自身の右手を差し出したノルベルグ選手。つい数分前に自身が障害について話した右手で、しっかりと私の手をにぎり「ありがとう」と。私はといえば、レースのスタートからゴールまでを応援し、追いかけた選手が目の前にいるだけで緊張してうまく質問ができない。ノルベルグ選手はそんな私のメモをのぞきこみ、取材の意図をくみ取って話してくれた。
思いがけない握手の強さに、周囲の応援を一手に受けるプロアスリートでありながら、ひとりひとりの応援者に心から感謝する気持ちがあふれているのを感じた。