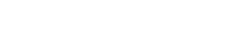■「地の利」をアピール
2020年東京パラリンピック開幕まで2000日を切り、パラスポーツへの注目も日増しに高まっている。そんななか、2月中旬に北海道旭川市で開催されたIPC(国際パラリンピック委員会)クロスカントリースキーのワールドカップ(W杯)旭川大会はパラスポーツの国際大会を日本で開催する意義について考える、よい機会となった。

昨年は、ブラインドサッカーの世界選手権が東京で開催されたり、2020年への強化の一環で外国チームを招聘し親善試合を行った競技もいくつかあった。とはいえ、まだ数は少なく、日本選手が海外に出かけることが一般的だ。例えば、クロスカントリースキーでは、今回の旭川W杯は98年長野パラリンピック以来、17年ぶりに国内で開かれた国際大会だった。
そんな背景で行われたW杯旭川大会を、まずは競技面から振り返ってみたい。クロスカントリースキーのW杯は年間3~4回程度行われ、選手は上位に入ってポイントを重ねるとパラリンピック出場につながる重要な大会だ。これまでは北米や欧州を中心に開催されており、旭川はアジアで最初の開催地となった。
今季のW杯全3戦中の2戦目が旭川大会で、競技日程5日間で3カテゴリー(座位、立位、視覚障害)合わせて男女25種目が実施されたが、エントリーした選手は日本をはじめ、ロシアや米国、ノルウェーなど9カ国から約50選手。日本選手を除くと、8カ国約30選手だった。昨年12月の第1戦フィンランド大会での12カ国約100選手に比べると物足りないが、直前の1月にアメリカで世界選手権が行われ、15カ国約130選手が参加したことを考えると、旭川は日程的に厳しい条件だったのかもしれない。
ただ、来日した選手や関係者からは旭川大会は高い評価を受けた。一つは雪質の良さで、欧米の会場はほとんどが人工雪だが、日本屈指の寒い都市で知られる旭川は自然雪だけでコースが設営できる。また、会場となった富沢クロスカントリースキーコースは空港や市街地からのアクセスも良く、今回選手村となった市街のホテルからはシャトルバスで約20分という近さだった。

冬季パラリンピックは2018年の韓国ピョンチャン大会、つづく22年大会もカザフスタンのアルマトイか中国の北京のいずれか(今年中に決定)と、アジアでの開催が続く。今後、アジアへの注目は高まる見込みで、旭川は今後の大会誘致のほか、合宿地としてのアピールもできたのではないかと思う。
■思い切った参加が開く、可能性
日本選手は19名。地元開催ということで、通常のW杯では参加できない選手にもチャンスが広がった。例えば、オープン参加枠で中・高校生が国際大会を経験できたことは日本チームにとっても収穫だ。
また、車いすソフトボールなど他競技からの参加者もいた。例えば、ソチ・パラリンピックで銅メダル獲得後は車いす陸上に専念している久保恒造選手(座位/日立ソリューションズ)も一時復帰して出場。さらに北海道出身の久保は、「地元開催の大会を盛り上げたいし、シットスキーの普及にもつながれば」と、陸上仲間にも参加を呼び掛けた。
その一人、廣道純選手(座位/プーマジャパン)は、「日本開催の国際大会は、より多くの人から注目される。それは障がい者スポーツ全体にとってもプラスになる」と誘いに応じたが、畑違いの競技の選手やスタッフとの新たな交流に、「学ぶことが多く、メンタル面で刺激を受けた」と別の効用もあったという。

「スキーは初挑戦だった」という松永仁志選手(座位/グロップサンセリテ)も、「楽しかったし、冬場のトレーニングとして陸上にも生かせそう」と予想以上の手応えを口にするなど、新たな発見や可能性を見出す、いい機会になったようだ。
また、クロスカントリースキーのパラリンピアン、佐藤圭一選手(エイベックス)はスキー練習の一環で自転車などに取り組んだことをきっかけにパラトライアスロンにも挑戦。現在は本格的にリオデジャネイロ・パラリンピックを目指すほど力を伸ばしている。一選手の複数競技挑戦は選手不足が課題のパラスポーツには一案だ。今大会のような大会出場が可能性を広げることもあるかもしれない。
■観戦をきっかけに、広がる世界観
大会観戦は無料だった。が、来場者数は土日が約500人ずつ、5日間合計では約2000人にとどまった。大会のPR策としては繁華街にポスターや宣伝旗が掲示されたほか、大会缶バッジを販売し、協賛店に持参するとサービスが受けられるキャンペーンも実施された。数店舗に取材したが、あまり機能していないようだった。開幕前や開催中に大会をどう告知し集客するかは今後の課題だろう。

とはいえ、会場では子どもたちの姿が目立っていた。学校単位での観戦や、レースの前走を務めた地元スポーツ少年団の子どもたちなどだ。彼らは、選手のパフォーマンスに歓声を上げ、日本人だけでなく、外国選手にも物おじせずにサインや写真撮影をねだったりしていた。久保選手は、「障がい者スポーツを身近に見て感じるチャンスは少ない。今回の経験で子どもたちの視野が広がってくれれば」と話し、バンクーバー金メダリストの新田佳浩選手(立位/日立ソリューションズ)も、「『スキーをやってみたい』と思う子が増えたり、海外選手の体格や滑りを実感することで、幼いうちから『世界』を意識することにも役立つのでは」と期待を寄せた。
カナダのベテラン、ブライアン・マキーバー選手(視覚障害)も、「障がい者のW杯はどこも観客が少ないが、旭川では多くの子どもたちの声援に励まされた。カナダの子どもにもこんな機会があればいいのに」と話していた。
■地元総出で盛り上げた、初のW杯
旭川はクロスカントリースキーをはじめスポーツの盛んな町として知られ、また10年ほど前から障がい者スポーツの大会もいくつか運営してきた。それらの大会運営に携わってきた人々の胸に、「日本初のW杯は旭川で開催したい」という思いが自然と芽生えていたという。

そうして引き寄せた念願の大会を実行するにあたり、「旭川の力を結集し、地方でもできることを示したい」と奔走。公的な助成金などに頼らず、企業や個人など約80のスポンサーを集め、温かな手づくり感あふれる地元色の濃い大会をつくりあげた。
例えば、選手に贈られるメダルの制作は、地元の北海道雨竜(うりゅう)高等養護学校と美深(びふか)高等養護学校に依頼した。生徒たちは味わい深い陶器製のメダルと、北海道産ナラ材で触り心地にこだわったディスプレイ用の盾を完成させた。また、和服をリフォームしたメダル収納用袋は地元の福祉施設が制作に協力した。

今大会金メダリスト第1号となったオクサナ・マスターズ選手(座位/米国)は、「高校生の手づくりなんて、とってもスペシャル。今までもらったなかで一番素敵なメダル。大事にします」と地元の心づくしに感激していた。
運営を支えたボランティアもほぼ地元市民で、「国際大会を手伝いたい」と高校生から最高76歳まで約200人が集まった。その多くは、「ボランティア初心者」や「障害者スポーツは見たことがない」人だったようだが、コース設営や飲食ブース、通訳などで大会を支えたり、選手のパフォーマンスを目の当たりにして、「やりがいがある。参加してよかった」「障害があるとは思えない選手の迫力やスピード感に驚いた」といった感想が聞かれた。新田選手は、「地元開催だからと、これまで障害者スポーツに携わったことのない人たちまで参加してくれたことに意義がある。この体験を周囲に伝えてくれることで、パラスポーツが広がるチャンスにもなる」と喜んだ。
競技会場の盛り上げにも地元パワーが光った。旭川では有名な、青いタイツ姿の「ニッポンマン」を中心にした私設応援団が今大会でも活躍した。日本選手だけでなく外国選手も万遍なく応援しようと、全9カ国の国旗セットを多数つくって一般観戦者にも配り、滑ってくる選手の国名を皆で連呼しながら国旗を振った。心のこもった応援は、「スタート直後に祖国の名前が聞えてきて励みになった」「他のW杯よりも応援の数が多く嬉しかった」と、外国選手にもしっかり届いていた。
場内放送もよかった。放送班リーダーの今野征大さんは旭川スキー連盟所属の高校教員で、以前からさまざまなスキー大会でMCを担当している。障害者スキーの場合はクラス分け(*)など特有のルールの説明が欠かせない。また、事前に取材して各選手のエピソードなども盛り込み、「選手への親近感を増す工夫」なども心がけたという。 (*)クラス分け:競技を公平に行うため、各選手の障害の内容や程度を診断し、類別すること。
スポーツ大会の運営には救護など医療機関の支援も欠かせない。特に障害者スポーツの場合は大会前にクラス分けの設備も必要になってくる。旭川大会を支援した機関の一つが旭川医科大学だ。同大学はスポーツ医学に強く、その範囲を障がい者スポーツにも広げているそうで、大会関係者は「心強い存在」と話していた。
■まずは一歩。土台はできた
こうして町をあげて取り組んだW杯。閉会式では、IPCノルディックから派遣され、大会運営を司ったテクニカル・デリゲイト(審判長)のゲオルギー・カディコフ氏が、「旭川大会は大成功だった」と評価。外国選手団からは組織委員会や市民に対する感謝の言葉が並び、「これまで参加したW杯の中でアサヒカワが一番」と話す選手さえいた。

旭川市出身の荒井秀樹日本代表監督も地元開催のW杯実現に奔走した一人だ。「過去のパラリンピック開催都市の多くは大会後にも国際大会を再び開いている。でも、日本は長野パラリンピック以降、開催できなかった。長野大会で培ったノウハウやマンパワーを活かし続けていれば、今頃、日本の障害者スポーツはもっと強く、もっと可能性が広がっていたのではないか・・・。そんな風に残念に思う気持ちが、旭川大会開催の動機のひとつでもあった」と明かす。
大会、まして国際大会となれば、運営には多大な労力が必要だ。でも、大会運営という実績やノウハウは、経験という名の「レガシー(遺産)」だと思う。今回の旭川には課題もみられたが、開催したからこそ実感できた貴重な気づきであり、それは次回に向けての財産になる。大会をきっかけに、市民にパラスポーツに対するポジティブな見方や考え方が生まれ、根付くことも期待できる。
大切なことは、打ち上げ花火のような一過性の祭りでなく、大会開催を継続させることだろう。こうした挑戦が旭川だけでなく、他の都市にも広がって多くの国際大会が開かれることを願う。