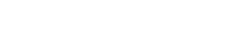2025年4月10日から3日間、静岡県富士水泳場で、国際パラリンピック委員会(IPC)主催・日本パラ水泳連盟主幹による「パラ水泳ワールドシリーズ富士・静岡2025」が開催された。

世界記録を起点とする戦い──異なる障害クラスが共に泳ぐ
本シリーズの最大の特長は、世界記録を1000ポイントとする相対評価により、異なる障害クラスの選手同士が同じレースで競い合える”WPSポイントシステム”の導入だった。
このシステムのもと、男子100m平泳ぎでは日本の山口尚秀(SB14)が1:02.64で自身の世界新記録(1053ポイント)を更新。女子100m平泳ぎでもロシア(NPA)のLUKIANENKO Daria(SB11)が1:21.11(1013ポイント)と、クラスを越えた圧巻のパフォーマンスを見せた。


今回世界記録を更新した山口とロシアのLUKIANENKO は、共に2019年ロンドン世界選手権に初出場した。2人が、男・女それぞれ複数種目で優勝・表彰台に立ち、マルチメダリストとしての強さを改めて示したことも、今大会のハイライトの一つである。

そして、静岡県出身のパラ水泳のレジェンド・鈴木孝幸(SB3)は、自身の“原点の種目”である男子50m平泳ぎで49.49秒(866ポイント)を記録し優勝。アテネ2004パラリンピック・デビュー以来、6大会連続出場しつづける鈴木が昨年パリ大会で16年ぶりに自己ベストを更新する快挙で湧かせ、本シリーズでもその健在ぶりを地元で印象付けた。
日本若手の成長──川渕大耀、松田天空、田中映伍らが大活躍
今大会でとりわけ注目だったのは、男子400m自由形ユースファイナルで4:18.16(943ポイント)を叩き出し、A決勝3位の記録を残した川渕大耀(S9/NECグリーン溝の口)である。決勝でタイムを10秒以上更新し、自身初となるアンダー21枠での世界選手権派遣を決めた。「シンガポールでの世界選手権にチームメイトと一緒に行きたい」という想いが、力強いラストスパートを支えたようだ。

川渕同様、半年前に初めてパラリンピックの舞台を経験した田中映伍(S5/東洋大学)が順調な成長をみせ、大会1日目・男子50m背泳ぎと50mバタフライの2種目でアンダー21代表としての派遣が決定した。とくに50m背泳ぎでは36.08(969ポイント)Aファイナルで優勝、持ち味のキックと終盤の粘りで観客席を沸かせた。50mバタフライでも疲れを感じさせない泳ぎで34.76(918ポイント)で派遣標準記録をクリアした。着実に国際舞台への階段を上っており、次世代のエース候補として存在感を示した。

一方、日本代表の強化プログラムリーダーを務める上垣匠氏は「大会の目的の一つは若手の育成という部分が大きな課題としてあります。アンダー21では、川渕、田中の2名というのはちょっと寂しいなと感じています」とまず課題について話していた。東京パラリンピックから2大会連続出場する日向楓(S5)や女子の前田恵麻(SB9)らアジアでは強い選手たちが、自国開催の機会を活かしきれなかったことが上垣氏の脳裏にある。


また上垣氏は「こういう競争力の高いポイントレースの中で競技をすることによって、アスリートとしての強さという部分が磨かれると思っています。この厳しい結果というのは、今の実力だろうなと感じますし、国内で開催できたことは、選手たちにとっても非常に<速さ>だけじゃなくて、<強さ>にも繋がる機会になったのかな感じています」と、ポイントで競う大会の開催意義を語っていた。


男子100mバタフライでは、松田天空(S14)が57.75秒で940ポイント、村上俊也(S14)が57.83秒で937ポイントと、ともに高ポイントを記録して1位・2位、日本の知的障害クラスの成長を示した。
アジア勢の躍進──香港、NPA、イラン、そして中国
今大会には、パリ大会で世界12位(=アジアでは中国に次ぐ2位)の実力のある我が国に、まだ記憶に新しい東京2020パラリンピックのイメージを抱いてきた選手も少なくなかった。さらに来年は「愛知・名古屋2026アジアパラ競技大会」が開催されることもあり、今大会にはアジアからクラス分けを受験するために来日した選手も多かった。「日本チームを目標に追いつけ、追い越せで頑張っています」とマレーシアチーム9人を率いて来日した峰村史世氏(元日本代表監督を務めた)は話していた。

男子50m自由形ではイランのZARIF POURESMAEILYAZDI Abolfが25.94(957ポイント)の記録で優勝し、マレーシアチームもMOHAMMAD Abd Halim(S8/MAS)が銀メダルを獲得した。日本の木村敬一(S11/東京ガス)は銅メダルだった。各国がトップ選手を送り込むワールドシリーズの場が、アジアを含むグローバルな成長の媒介となっていることが証明された。

男子400m自由形A決勝では、ロシアBERDNIK Rodion(S14/NPA)がパリ3位相当のタイム(4:09.17)を叩き出し競技を牽引したなかで、松田天空(S14)が喰らいつく泳ぎをみせた。
パラリンピックの“その先”へ──見えてきた地域課題と次世代育成
指導者らの談話からも、本シリーズの意義と課題が明らかになった。日本知的障害者水泳連盟の谷口由美子ハイパフォーマンスディレクターは、世界選手権を見据えた育成体制や評価制度の見直しを進めていると語った。今後は、ランキング制からタイム基準へと移行し、育成選手の強化をより柔軟に進めていくという。


また、国際クラス分け受験や、施設バリアフリーの整備状況、宿泊体制などの運営面も課題が問われた。パラ水泳の国際大会は、競技に専念するのみではなく、「インクルーシブな社会」の成熟度を図る場としても注目することができる。
世界は水面からつながる。
「世界記録との対話」を通じて、誰もが真剣勝負できる舞台が日本にも生まれた。静岡・富士の地に咲いた初のワールドシリーズは、未来の選手、そしてパラスポーツの価値を社会に問いかけるレガシーとなるはずだ。
この大会をきっかけに、より多くの人々が「パラ水泳の面白さ」に触れて応援し、一人一人が「多様性の社会」に参加する、まちづくりの広がりが生まれることを願ってやまない。
(写真取材・秋冨哲生)