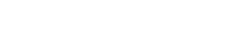若手のパラリンピアンたちは
トークショーの最後に、東京パラリンピックで活躍した若いパラリンピアン4人が最近の普及活動など、考えていることをお互い語るなかでメッセージを届けた。

PAJ創設時の先輩パラリンピアンの苦労と大きく異なるのは、競技そのものを仕事にできている選手が多いところ。4人の選手の活動を普及中心にをまとめると・・・。
岩渕幸洋(卓球、東京パラ旗手)

普及イベント「IWABUCHIオープン」という自分の名前のついた卓球イベントを主催している。
「初めて出場したリオ大会でパラリンピックの凄さを伝えたいというのがきっかけだった。卓球をつたえていく時に、広い体育館では、いろんなクラスがやっているけど、なかなか見やすく届けられない。選手の真剣勝負や駆け引きを目の前で見れる機会を作りたいと思って企画しました。見て面白いと思ってもらい、競技そのものを知ってもらうことにつながればと思っています」
2012年に国際大会へ初めて出場し、2013年に東京大会がきまった。「僕って障害者ってわかりにくいタイプなので、リオの時はああパラリンピックの選手なのか、っていう程度だったんですが、東京が決まって近づくにつれて、終わってからも声援が大きくなってきたのを感じます。パラリンピックってものの認知度があがり声援が黄色くなったのを肌で感じます」
木村敬一(水泳)東京パラリンピック金メダリスト)

「私たちは、先輩方のたゆまぬ努力でトレーニングができる世代。何の不自由もなくNTCに24時間入れるIDカードを発行してもらっている。パラスポーツというものがエリートスポーツとして認知された。気持ち以上のものをもらっていて、エリートスポーツとしては、私たちはもう頑張るだけでなく、勝たねばならんというものだと思います。競技に専念できる環境で、一般社会との距離も離れていっている。これまでは仕事をしながら競技活動していたが、僕たちは競技が仕事になっていて閉鎖的。接する人はコーチやトレーナーだけとなっている。一般社会との繋がりをもっている人が財産だと思います。狭い世界で自分達は生きている。アスリートもそうだが競技のなかで完結してしまう。わたしの場合水泳だし、そこでの人間関係が強固になっていく。それは寂しい。今後はPAJで競技をこえた友達づくりをしていきたい。河合さんたちの創成期にやっていた会話ができない選手もいるんじゃないか?と思う。このメンバーで考えていたのは同世代で集まれる努力をしたいなと。進学、就職、出産、親の介護などいろいろあると思います。そのなかで社会との繋がりがある人がいればと思うし。アスリートとして社会人として自立していけるような会にしていきたい。
永瀬さんの話とつながりますが、海外のパラリンピアンに情報をいただいて選手会ができた。私たちも海外に追いついていかないといけない。東京大会という最大のイベントを開催したので、海外に誇れる日本のパラアスリートにならなければいけない」
太田渉子(ノルディックスキーメダリスト、パラテコンドー)

「大日方さんたちと冬の大会から参加した。パラの環境もメディアも変わって行った。たくさんの人に見てもらえた。
2014年で一度競技を引退しています。テコンドーは東京が初めての競技だった。スキーについても、普及ということで関わらせてもらっている。選手を身近に感じていただくことを意識しています。
社会との関わり方は、アスリートだと競技に集中しアスリートファーストなどといわれるなかでのびのびとやらせてもらっているが、私の場合アスリートをやめた後もCSR部門で仕事をさせていただいています。仕事が大変なこともあるが、会社でも仕事をチームでやっている。会社に貢献できるように、スポーツで培ってきた経験、知識を企画に落とすこともできると思うし、させてもらっています」
瀬立モニカ(カヌー)

「今日は(PAJの)中にいる人たちが内側から変えていくエネルギーの強さを感じた。地元の東京都江東区のすべての学校の授業をまわっています。東京大会への熱量を止めてはいけないと思っている。パラリンピアンの強みは身近でいること。中学や小学校の偏見のないところでかかわってもらうことを江東区のパラリンピック後のレガシー事業として立ち上げてもらって、1時間は話をし、もう1時間は一緒に楽しもうというアクティビティをやっている。パラリンピアンは生きる教科書だと思う。その中で、「意外と普通なんですね!」っていわれたのが印象的だった。
大学在学中は他の学部の学生「何のためにスポーツやるの?」みたいなことを言う、違う価値観を得ることができたが、最近は寂しくもありますね」
(20周年インタビュー:NHK中野淳さん 校正・そうとめよしえ)