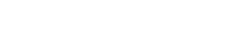パラスポーツは人々の情熱が原動力

1983年にカザフスタンで生まれたポポフは、7歳の時に家族とドイツに移住。その後、9歳の時に骨肉腫が発覚し、左足を膝上から切断した。2001年からドイツ・ブンデスリーガのフットボールクラブ『Bayer 04 Leverkusen』を擁する総合スポーツクラブ『TSV Bayer 04 Leverkusen』ので働き始めると同時に、同クラブの『Parasport TSV Bayer 04 Leverkusen』でパラアスリートとしてのキャリアをスタートさせた。
頭角を現すと、2004年のアテネから、パラリンピックでは4大会連続で、金メダル2つを含む計6つのメダルを獲得。2016年にマークした走り幅跳びの6m77は、現在も世界記録として残る。
ドイツ国内でも著名なアスリートの一人であるポポフの考えは、マスメディアでも時折紹介されている。彼は、パラリンピックとオリンピックは独立しているべきだという考えを持っている。
「オリンピックはビジネスであり、また、常に“競争”だけに関心が行きがちだ。人間同士の繋がりについては、あまり意識が喚起されない様にも思う。例えば、選手村で皆が共有できる場所には滞在せずに、5つ星ホテルに宿泊する選手もいる。それに比べて、パラスポーツは人々の“情熱”が原動力になっている部分が大きいと思う」
今回の競技後、ミックスゾーンでのポポフの言葉である。以前、日本のメディアにも同様の意見を語っている。オリンピックを否定しているというよりは、スポーツの祭典としての本来の在り方に立ち返るべきではないだろうか、という提言なのかもしれない。こうした言葉からも、彼の考えを窺い知ることができる。
ライフワークとしての義足ランニングクリニック
そんなポポフの“情熱”は、自身の競技外にも向けられている。
先述したドイツの福祉機器メーカー『ottobock』と共に世界中で行ってきた、義足ユーザーの為のランニングクリニックである。日本でも2015年にスタートし、今秋にも開催予定だ。初めてスポーツ用義足を履くという人から、既にパラアスリートとして活躍する人まで幅広く受け入れ、オリジナリティとユーモアに溢れたコーチングに評価も高い。山本も講師として参加している。
そのランニングクリニックは、今回、ベルリンでも開催された。8月23日。ポポフのラスト・ジャンプから2日後のことである。ヨーロッパ10カ国(イタリア、スイス、ドイツ、ポーランド、トルコ、オランダ、チェコ、フランス、ルーマニア、ハンガリー)から12名が参加し、初めてスポーツ用義足を履いたというオランダ出身の両足下腿義足の青年は、嬉々として芝の上を駆けていた。
「速く走ろうとするな。お尻にコインを挟む様に力を入れて足を前に引きつけるんだ。力の加減を左右対称にして、重心はまっすぐに」
メインスタジアムに隣接するサッカー場にポポフの声が響く。翌日はメインスタジアムへ移動し、実際にトラックを利用してのセッションが行われた。

ネガティブな感情と闘い続けたい
ジャパンパラ陸上の競技後は「(引退したら)ジャンクフードを食べたりビールを飲みながら、皆を応援していきたい」とジョークを言っていたポポフだが、引退してからの活動方針は明確である。
それは「パラスポーツを世界中に広げていく」ということだ。ポポフは言う。
「自分にはできない、不可能だ……。そんなネガティブな感情と僕は闘っていきたい。私たち(障害当事者)のQOL(Quality Of Life=生活の質)向上の為に。そして、人々にとってスポーツがもっと身近で親しみやすいものになるように。日本は2020年に向けて多くの準備が整っていると思うけれど、私を必要としてくれて、私にできることがあれば、サポートしていきたい。私は日本という国も大好きだから」
最後に、ポポフに尋ねた。
――あなたが思う、“スポーツの良さ”とは何ですか?
「スポーツの良さはモチベーションを高め、人々を繋ぐものだという点だ。そして、大切なことは誰に対してもいつでも開かれているということ。スポーツは最高の薬であり、人々をポジティブな考え方にする可能性を秘めている。一人ひとりが夢を信じ、その実現に向けて動くことができる原動力になりうるものだと思う。私たちは「不可能だ」なんてことは言わない。私にはできる。私たちにはできる。この思いの循環が、人々の心を開き、互いのリスペクトを強固なものにしていくと思っているよ」

(取材協力/Min Wu、谷本啓剛、校正・佐々木延江)
→Next page English text