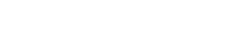韓国の各地から寄せ集められた大型バス内は個性的で華やかなカーテンに電飾。大画面テレビにはドライバーの好みの番組が。朝はニュース、土曜の夕方には歌謡曲ショーが流れ、日本の氷川きよしを思わせる“演歌スター”が自慢の歌声を披露していることもあった。コリアンな雰囲気に包まれるなか、乗客たちは目的のベニューへ向かい無言で座っていた。

パラリンピック期間中のメディアバス内の光景である。
平昌パラリンピックのベニューは、セレモニー全般が行われる平昌オリンピックスタジアムを中心とした平昌(ピョンチャン)市(山岳地帯;アルペンシア・バイアスロンセンター/クロスカントリースキーとバイアスロン、ジェンソン・アルペンセンター/アルペンスキー、スノーボード)と、江陵(カンヌン)市(沿海都市;アイスホッケーと車いすカーリング)に分かれている。遠いベニューへはバスで1時間程度かかる。
競技に出場する選手たちは、平昌の選手村を起点に各競技会場に散っていく。車椅子を利用している選手・関係者のために、車椅子のまま乗車可能なバスが導入されていた。
では、観客やメディア(我々)、ボランティアの移動についてはどうか?
会場間の移動にバスが使用されていることは選手と変わりない。しかしメディアの移動で使用されているバスは、普段は韓国内の各地で使用されている観光バスが会場に集められ、側面に「PyeongChang2018」という巨大なステッカーを貼って、オリンピック・パラリンピック仕様にしたものである。それらはほぼ“ノン・アクセシブル”だった。つまり車椅子ユーザーは車椅子ごと乗り込むことができないものであった。

今回パラフォト平昌取材班には、車椅子ユーザーのフォトグラファー・Gがいた。片足が不自由なため、ケンケンや同行者の肩を借りて移動も可能だが、撮影時は重いカメラ機材と共に移動するため電動車椅子を使用するのがGの撮影スタイル。バスの荷台に車椅子を積んで座席によじ登ることもできる。しかし、全ての車椅子ユーザーにそれができる訳ではない。一般バス以外の交通手段を使って、競技会場に向かわなくてはならない。本来は車椅子を使う観客やボランティアも想定しなくてはならないだろう。
この状況を受けて、大会運営側はメディア向けに『TMAタクシー』と呼ばれる手段を用意していた。“TM”は“Media Transport”の略で、これに“A”(Accessible)が加わったものだ。それは、車椅子のまま乗車可能なタクシーである。

パラリンピックでは、取材申請の際に車椅子ユーザーかどうかのチェックがある。すでに氏名や人数が把握されている。利用手順はシンプルだ。現地で大会運営側に利用の旨を伝えると、『TMA』と書かれた緑色のステッカーがアクレカードに貼られる。その後は、事前に電話で予約を取り、出発地、時刻、目的地、名前、登録番号、乗車人数を伝えれば、その場所にウェルキャブ(福祉車両)が現れ、会場間、宿舎から会場まで送迎をしてくれる。
筆者はスノーボード、クロスカントリー、アルペンスキー、アイスホッケーの計4度、Gと共に行動し、TMAタクシーを利用した。お互い英語を母国語としない国同士のやりとりで、多少手間取ることや、行き違いもあり、焦ることがあったが、一度乗車してしまえば大変有用なシステムだった。
そんなこんなで、TMAタクシーを乗りこなし(?)、我々は各競技会場に遅刻なく到着することができた。

ある日、IPC(大会を主催する国際パラアリンピック委員会)オフィスのメディア・コミュニケーションの担当者を尋ねて状況を聞いてみると、 「選手団や大会関係者の輸送には問題はなかったと思う。メディアや観客の輸送にはやや課題があったかもしれない」と言う。 恐らく、苦労して解決策を練ったことだろう。自分の質問に気を悪くしたかもしれず申し訳なかったが、 「(2020東京に向けて)冬と夏で異なり、平昌と東京では街の形態も異なるので単純比較はできないけれど、取り組むべきテーマの一つだと思う」とも話してくれて、質問者としての意図も伝わったようで、安心した。
今大会期間中のメディアエリアで車椅子ユーザーに出会う機会はさほど多くはなかったが、何人かはいた。ハンディを持っていても職業選択の幅が広がっていくにつれて、障害のあるジャーナリストも増えていくだろう。 冬季競技の取材は自然環境が相手の競技が半分以上を占め、夏季大会よりも会場がバリアフルである。

実際、TMAタクシーでベニューに到着した後も、Gがフォト・ポジションまでたどり着くのが大変だった。なにしろ、足元が雪面で、凹凸が激しい。 結局、ボランティア・スタッフに協力を仰ぎ、4人がかりで車椅子ごとGを運んだ。ハイテクとローテクの合わせ技で、ようやく取材を行うことができたのだった。
「理想の運営ができなければ、別の手段を考える」TMAタクシーを通じて、バリアフルな状況もパラリンピックの理念に叶う“機転”として運営側に垣間見ることができたように感じた。
(校正・佐々木延江)