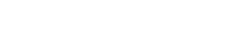パラリンピックを契機とした「共生社会をどう作るか」をテーマに、スポーツや障害者への理解と関わりを深める授業が、6月23日(金)立教大学で行われた。
講師を務めたのは、株式会社WOWOWでパラリンピック・ドキュメンタリーを制作する太田慎也さん。授業は東京パラリンピックでホスト役となる東京都の応援プロジェクト「チーム・ビヨンド」の紹介とともに行われた。
太田さんは、世界中のパラリンピアンの中から毎年8人を選んで、競技人生に迫るドキュメンタリーシリーズ「WHO I AM(=自分)」を3人ずつの8チームで撮影、2020東京パラリンピックまでに40人を取材する。すでに昨年中に最初の8人を取材・撮影し、作品を発表している。
太田さんは授業で、撮影した映像や選手たちの言葉をダイジェスト版に編集して、パラリンピック・スポーツの魅力を伝えた。
取材のなかで、取材者自身の障害者像が変化したという。
太田さんたちがパラリンピック・アスリートに出会った初取材は、2015年イギリスのグラスゴーでおこなわれたIPC国際パラリンピック委員会の水泳世界選手権だった。そこには、鍛え抜かれた肉体と、自信に満ちた表情があふれていた。日本代表も含めて、「かわいそうな障害者」もしくは「障害を乗り越えて頑張る障害者」はいなかった。通常のスポーツ・エンターテイメントの取材現場であり、彼らはトップアスリートたちだった。
リオパラリンピックを目前に控えたブラジルの手足のないダニエル・ディアスは7つの金メダルを獲得してみせてくれ、病気で右脚を失ったが障害を自分の最高のチャームポイントだと自慢するオーストラリアのエリー・コールに出会った。
多くの新記録が更新された激闘の日々は、世界最高峰のスポーツを伝えようとする取材者に興奮と驚きに満ちた現場となった。
また、取材を進めるうちに、障害があるアスリートの人生やスポーツが同じではないこと、選手としてそれぞれ多様であることも見えてきた。
「握手しようとした人が右手がない、引いちゃう、自分たちの方に、へんな間があるんです。これが自分たちの障害だと思った。
選手を取材するまでは、かわいそうな人が頑張っている世界だと思っていた。しかし、個性や多様性を目指す社会で、いまだ障害のある人との接し方を知らない自分のたちにこそ障害がある。障害のあるなしではなく、人生のヒントになることを伝えることで、我々の側が持っている障害を乗り越えたい」と太田さんは言う。
授業のあと、ある学生は「かっこよかった!」と。
太田さんは、「それを伝えたかった。かわいそうじゃなく、かっこいい。3年後、この街にみんな来ます!」と映像で紹介した選手たちが東京に来ることをあらためて伝えた。
現在、2020東京パラリンピックをテレビなどメディアで観戦したい人は72.3%、スタジアムで直接観戦したい人は18.3%。
東京都では、大学の連携でこのような授業を通じて、スタジアムでの観戦を増やすことを目指している。立教大学では、「パラリンピックを契機とした障がい者スポーツ支援(担当:松尾哲矢教授)」として14回の授業が企画され、今回はそのうちの11回目で、毎回全学年から関心のある学生が聴講している人気授業となっている。